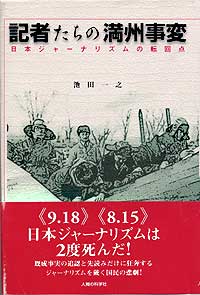民族幻想論
あいまいな民族 つくられた人種
スチュアート・ヘンリ:著 解放出版社:刊 202ページ 2,000円+税
|
|
|
「さて、民族問題については本文で詳しくふれていきますが、このとき、とくにわたしの目を惹いたのは、2001年9月14日付の朝日新聞の第4面の記事でした。左上の囲み記事のなかで、<アフガニスタンの政権を握っているのはタリバンというグループであり、その大半を占めるのはパシュトゥン人である>と書かれています。そのすぐ下の別の記事では、<同時多発テロの直前に、タリバンと敵対する北部同盟の最高指導者だったマスード元国防相が暗殺されたのは、テロリストたちの一連の犯行である>とし、<マスードはタジク族の出身である>とあります。
はて、なぜ片方はパシュトゥン人で、もう一方はタジク族なのでしょうか。○○人という呼び方と、○○族という呼び方の違いの基準をどこにおいているのでしょうか。そこにはなにか偏見、わるくすると差別意識、もしくは誤解を生むものが含まれていないでしょうか。わたしたちはイギリス族とかフランス族とかいうでしょうか。」
|
目から鱗の一冊。
「人種」は科学的・生物学的、「民族」は、人文学的(?いい加減・・・)区別かと思っていたら、どちらもあいまいで、混同して使われているどころか、それぞれの定義が全く政治的であることを知りました。
もし日本が、江戸末期に外国との対応を間違って、または他国がなんらかの意志を持って占領でもしていたら、“武士族”や“町民族”に分けられていたかも知れない、それくらいのものだそうです。
「白人」は、本当に「白い人」か?
「黒くても黒人といわれない人」は?などの実例を挙げて先入観を壊してくれます。
過去には、植民地で遭遇した“先住民”に対し、ヨーロッパの列強国に人々が、自分たちに理解できる歴史がないということで「歴史なき人々」、また、「サルの群とは大差はない。性向は獣と同じであり、外見は獣に劣る。」などと書いていたことさえあるそうです。
そして、「人種はある、しかし差別はいけない」という認識止まりの状態を批判しています。
巻末では、現代日本のメディアに現れた表現を実例を挙げて検証しています。
|